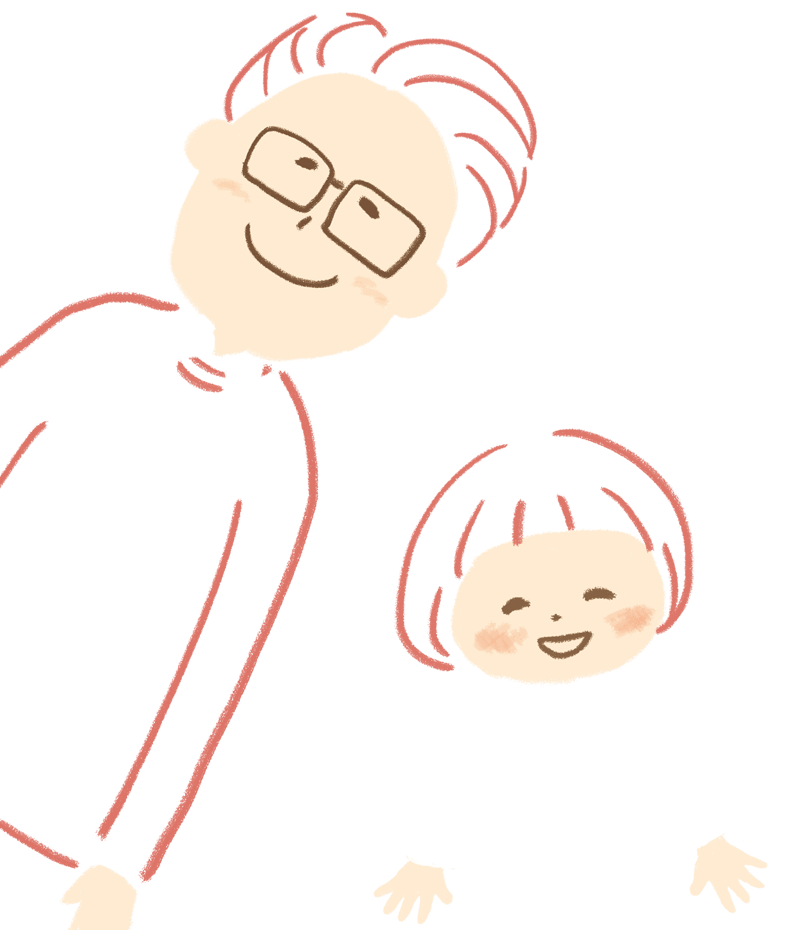
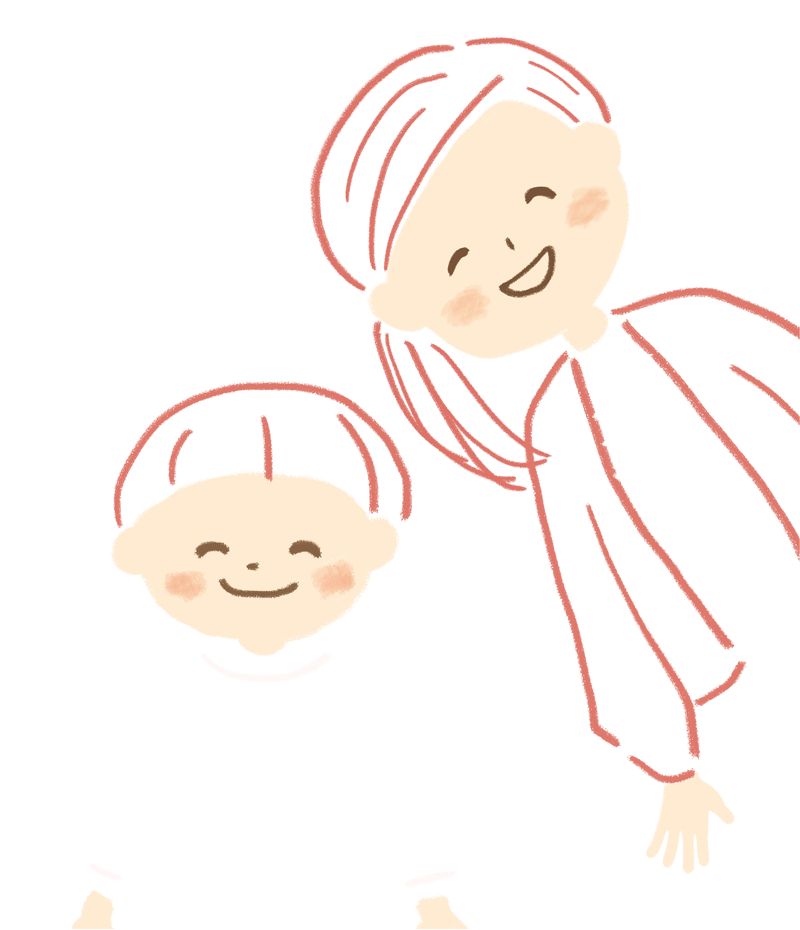
それぞれの事情で親と離れて暮らす子どもが、長野県内には約600 人います。
こうした子どもを自分の家庭に迎え入れ、さまざまなサポートを受けながら養育するのが「里親制度」です。
子どもの健全な成長を促すため、あなたも「里親」について一緒に考えてみませんか?

いいえ、違います。里親の種類は、主に2種類です。
それぞれの事情で親と離れて暮らす子どもを、
①親のもとに戻るまでや自立するまでの間、一定の期間(短期間~)養育する「養育里親」と、
②原則、特別養子縁組を結ぶことを前提に、縁組(法律上の親子関係)が成立するまでの間、「里親」として養育する「養子縁組里親」があります。

里親(特に養育里親)の養育をチームとして支える、「里親支援センター」など(※)のフォスタリング機関があります。
フォスタリング機関は、里親になる時の相談の段階からサポートを行い、研修や子どもを迎え入れる際の調整、養育の支援、養育終了後のアフターフォローなど、様々な支援を総合的に行います。
※児童相談所においても、専任の担当者が相談への対応や支援をしています。

子どもを育てるのに必要な生活費、教育費、医療費などが支給されるので、安心して養育できます。
生活費:約5万5千円(乳児の場合約6万4千円)/月
里親手当:9万円/月※養育里親の場合
(令和6年度時点)

一律の年齢要件はありません。
「養育里親」は、健康状態等を踏まえ、委託される子どもの養育が可能であれば里親登録が可能です。県内でも60歳以上で活躍する里親がいらっしゃいます。
「養子縁組里親」として特別養子縁組を希望する場合は、原則25歳以上であり、子どもが成人して自立するまで養育が可能な見通しが望まれます。
共働きや実子がいる家庭でも、登録が可能です。共働きの場合、保育所等の利用もできる制度です。
ただし、ご家庭の状況を踏まえ、委託される子どもの養育が可能であることが必要です。
このため、お子さんをはじめ、ご家族の理解と協力を得ることが大切となります。
(フォスタリング機関では、ご家族の理解のため、里親についての説明をすることができます。)
里親の環境は人それぞれ。そして、やりがいや難しさも人それぞれです。子どもたちに個性があるように、里親のあり方にもさまざまかたちがあります。
ほんの一例ではありますが、長野県内で養育里親として子どもたちに愛情を注ぐ方々にお話を聞きました。この記事が、関心を持っている方の一助となれば幸いです。

共働きの下崎さんご夫妻。子どもはなく、2020年に里親登録、同年に初めてとなる当時小学2年の男児・尚志くん(仮名)を受け入れ、3人暮らしは5年目を迎えました(2025年インタビュー時点)。
里親になろうと思ったきっかけを教えてください。

志展さん:夫が47歳、私が35歳のときに結婚しました。40歳まで不妊治療をしていましたが、治療をやめたタイミングで、回覧板に「赤ちゃんを数週間預かってみませんか?」という内容のチラシが入っていたんです。それで里親支援センター(※)に話を聞きに行って、受け入れたいと思いました。
※下崎さんが話を聞きに行った当時は、長野県の包括的里親支援事業委託先
眞澄さん:私は当初、反対でした。責任もあるし、二人とも仕事がありますからね。「ペットとは違うんだよ」と言った記憶があります。
志展さん:たしかに共働きということもあって、付きっきりの養育が難しいので、私も「トイレトレーニングもまだ」というような小さな子どもは無理だと思いました。なので、ある程度のことは自分でできる、小学生以上の子どもを希望しました。

どんな準備をしましたか?
志展さん:特に準備というものはありませんでした。ただ、計3日間の研修とその後の実習に行く時間が取れなくて、最終的には登録申請してから1年半かかってしまいました。なかなか平日に休みが取れなかったんです。
眞澄さん:当時は築50年以上経った古い家に住んでいました。寒い家ではありましたが、1部屋空きがあったので何とかなるだろうと思いました。心の準備というほどのこともなかった気がします。
大変なことはありましたか?

志展さん:最初の1年は大変でした。おんぶされたがったり、体当たりしてきたりで、ヘトヘトでした。歯磨きをしなさいとか、宿題はちゃんとやるんだよとか、いつも何かしら叱ってしまっていました。

眞澄さん:私は細かいことを気にせず一緒に遊んでばかりだったのでよかったことばかりですが、妻には苦労をかけたかもしれません。
大変なことがあっても続けているのはどうしてですか?

志展さん:やっぱりめちゃくちゃかわいいから。それと成長していく姿を日々見ていられます。ついこの間までケーキを食べるときは必ず口の周りに生クリームがついていたのに、もうきれいに食べられるようになったなあとか。
眞澄さん:私は精神年齢が一緒なので一緒になって遊んでいます(笑)。もともと趣味だった釣りにはよく一緒に行きますし、旅行にも行きますね。

志展さん:尚志くんが野球をしている姿を見て、他の親御さんが「かっこいいね」って褒めてくれたりするんですけど、「でしょ!」って返したりしています(笑)。自分の子だと謙遜したりするのかもしれませんが、「里親の特権だよ」なんて話しています。成長する姿が見られないお母さんのことを考えると、複雑な気持ちになることもあります。
周囲の人にも里親・里子の関係をお話ししてるんですね?

眞澄さん:そうですね。他人にはわからないようにしている里親さんもいますし、いろんな考え方があるとは思いますが、うちは名字も別で名乗っていますし、オープンにしています。
志展さん:ただ、なかなか「養育里親」について知っている人が少ないので、説明が難しいときもあります。里親イコール養子縁組ではない、ということをもっとたくさんの人に知ってもらえたらいいですね。

里親をやっていてよかったと思うのはどんなときですか?

志展さん:ドラマで赤ちゃんが産まれるシーンを一緒に見ていて、私がつい「産みたかったなあ」とつぶやいたことがあったんですけど、尚志くんが「おれ、いるじゃん!」って。「この家にいることは奇跡だよ」とうれしそうに言ったこともありました。うまくいかなかった時期もありましたけど、どんどん心を開いてくれていったのがうれしかったですね。

里親支援センターなどのサポートで、助かったのはどんなものですか?

志展さん:里親支援センターには、ちょっとしたことでも何かあればとりあえず連絡しています。本当に何でも相談していますね。児童相談所や学校などともスクラムを組んでもらっています。受け入れ当初は学校に行きたがらなかったんですけど、小学校と児童館が連携してちょっとずつ徐々に学校に慣らしてくれたり、本当にたくさんの人が関わってくれています。
眞澄さん:はじめは勉強もだいぶ苦手だったんです。でも、学校はそれも気にかけてくれて、成績は格段によくなりました。テストで100点を取ったときは、私が帰ってきたときに玄関まで飛び出してきて。なんだろう?と思っても、なかなか言わない(笑)。
志展さん:私は仕事中に3回も電話が来ました。で、夜に全員そろったところで100点のテストを見せられて(笑)。

どんなふうに成長していってほしいですか?

眞澄さん:私は一人でも生きていけるようになれといつも言ってますけど、妻はちょっと違うみたいです(笑)。
志展さん:里親制度では18歳になると委託解除(必要な場合は20歳まで)になりますが、私はずっとここにいてもらってもいいんです。何ならここから通える大学に行けばいいとも思っています。ただ、今は甘えん坊ですけど、これからどうなっていきますかね(笑)。


2019年に里親登録。翌年、当時2歳半すぎの結衣ちゃん(仮名)を受け入れる。2023年春、結衣ちゃんが年長にあがる時に実親のもとへ戻ったのち、2024年に3歳の凛ちゃん(仮名)の養育がスタート。高3と高1(2025年1月時点)の実子、夫と5人暮らし。
里親になろうと思ったのはどうしてですか?

宮下さん:実子が2人いるのですが、3人目どうしようかな、と思っているときに、たまたま里親支援センター(※)の広報物を見て、養育里親のことを知りました。子どもたちがわが家で楽しそうに暮らしているので、この中に入ったらきっと難しい環境で育った子も楽しい毎日を送れるだろうな、と思ったんです。
※宮下さんがチラシを見た当時は、長野県の包括的里親支援事業委託先

ご家族の反応はいかがでしたか?
宮下さん:当時小4だった下の男の子は弟か妹を欲しがっていたので大賛成でした。小6の長女は、私と一緒に福祉施設に行ったりして、いろんな子どもたちがいることを知っていたし、実際に接したりしていたので、抵抗はなかったようです。夫は驚いて、一度反対もされましたが、最終的には「がんばってみよう」と言ってくれました。
里親登録は夫婦ではなく、良江さんのみとお聞きしました。お一人で大変なことはありますか?

宮下さん:わが家は実子が小さいころから、夫は外で働いて、私は家を守るという昭和の価値観が強い家庭でした。役割分担がはっきりしているんです。実子の子育てのときと変わらないので、大変だとは思いませんでした。

ご自分のお子さんへの影響はありましたか?
宮下さん:最初は、結衣ちゃんのほうにかかりきりになってしまったこともあって、当時下の子が少し不安定になった時期がありました。ただ、そのサインを見逃さなかったので、毎週金曜の夜、里子が寝ついた後でプチ・パーティのようなものを開いて、会話の時間をつくるようにしました。あとは、どうしても食事の時間を一緒にすると小さな子にかかりきりになってしまうので、子どもたちと夕食の時間をずらしたりしました。
その後、変化はありましたか?

宮下さん:不安定だったのも最初の2ヶ月くらいで、あとはすぐ適応してくれましたね。そして、わが家にとって大きな出来事もありました。長女が結衣ちゃんと一緒にクレヨンでお絵描きをすることが多かったのですが、それがきっかけで美術に興味を持ち始めて、この4月から東京の美大に進学することになりました。私は娘の才能に気づいていませんでしたし、わが家にはクレヨンすらなかったんです。結衣ちゃんがいなければ娘の人生もまた違ったものになっていたかもしれません。

実親のもとに帰ったときはどんな気持ちでしたか?
宮下さん:本当にハッピーエンドだと思えて、うれしくて仕方なかったです。お母さんとお会いする機会もたびたびあったんですけど、徐々に母親として変化していったし、結衣ちゃんの祖父母の協力もあると知ったので、戻っても大丈夫だろうという安心感があったんです。
寂しさとどちらが強かったですか?

宮下さん:うれしさです! もともと1年くらいという打診だったんですけど、わが家で3年暮らしました。それも家庭というものに慣れるのに、ちょうどよかった気がします。里子にとっては、毎日同じ人(家族)とすごす、という経験が初めてだったので、やっぱり時間は必要だと思います。

昨年、受け入れた2人目の里子は委託期間が未定だそうですが、1人目と2人目で変化はありますか?
宮下さん:2人とも受け入れたのが3歳前後というタイミングが同じなので、心に余裕があります。1人目のときは、長期の養育だと別れるのが寂しくなってしまいそうなので避けようと思っていたんですが、経験を積んだこともあって、どんな期間であってもお家に戻れるなら笑って送り出せると思うようになり、今回は迎え入れました。
里親として、一番大変だったことはなんでしょうか?

宮下さん:最初は感情の表現がわかりづらくて苦労しました。笑顔でいたずらしたりするので。でも、次第に自分を見てほしいときにそうした行動をすることがわかってからは、とにかく愛情をわかりやすく注いできました。危ないことをしたときは「私の大事な結衣ちゃんを傷つけないで!」と本人に言ったり、「かわいい、大好き」といった言葉をできるだけ伝えるようにしていました。家事をセーブして、できるだけ時間をかけて接した日もありましたが、本当に最初のころだけですね。

実親との交流もあると聞きました。
宮下さん:結衣ちゃんが親のもとに戻ったあとも、お母さんから相談されることがあります。自分の子どもとそんなに年齢も変わらないので、言い方が失礼かもしれませんが、親のほうもかわいくてかわいくて応援したい気持ちです。
周囲のサポートはありましたか?

宮下さん:里親支援センターには困ったことを何でも相談していました。それと、里親仲間の存在は大きかったですね。LINEで相談するだけでなく、実際に会って話したりもして、支えてもらいました。
里親になってよかったですか?
宮下さん:そうですね! 安心して暮らせない子どもの人生を変えることができるかもしれないと考えると、里親ってすごいって思うんです。
実子がいることで里親になるのを迷っている人がいたら、どんな言葉をかけますか?

宮下さん:自分の子どもと同じように扱えるかを心配する人は多いと思いますが、同じように接する必要はないと思うんです。子どもにはみんな個性があるし、それぞれの長所にふれられたことも、やってよかったと思える理由の一つです。それと、わが家では、以前はまったく家事をしなかった夫が、結衣ちゃんが来てから料理とトイレ掃除をするようになりました。今では、休みの日は必ず何か作ってくれます。里親としての養育は大変なこともありますけど、乗り越えると強い絆ができるんじゃないかなと思います。


小川さんご夫妻には2人の子どもがいますが、すでに独立して遠方で暮らしています。2018年、俊明さん・つや子さんがともに69歳のときに里親登録。2019年、0歳2ヶ月の子どもを2ヶ月間養育、2019年には中学2年生を8日間受け入れました。現在も双方の家族と交流があります。
里親登録をするきっかけを教えてください?

俊明さん:長年、塾を経営してきたのですが、学習支援のボランティア活動を始めて養護施設の子どもたちと接することが増えてから、里親の必要性を感じるようになりました。もちろん施設で暮らすほうがいい子もいますが、家庭が必要な子もやっぱりいます。里親委託率が90%にのぼる国がある中、日本は20%台と非常に低いことは知っていましたし、何かできることはないかと思ったんです。

つや子さん:夫からその意志を聞いて、私も意義深いことだとは思いましたが、やっぱり子育ては大変ですし、最初は積極的ではありませんでした。でも、夫の情熱にほだされましたね(笑)。
不安はありませんでしたか?
俊明さん:里親登録したのが69歳のときなので、体力的なことも含めて不安はありました。ただ、児童相談所を信じてもいました。「69歳の人なら、こういう子がいい」という視点で、正しいマッチングをしてくれるだろう、と。
1人目となる生後2ヶ月の子どもの受け入れまで、どんな準備がありましたか?

俊明さん:準備というほどのことはありませんでした。登録しても委託されないという方もいらっしゃいますし、もしかしたら打診が来ないかもしれないなと思っていました。1年弱くらい経ったところで連絡がありました。
つや子さん:まさか生後2ヶ月の赤ちゃんとは、予想外でしたけどね(笑)。

俊明さん:さすがに小さすぎて大変だとも思ったんですが、「不慮の出来事で大変な状況になっているご家庭だ」という事情を聞いて、「ここで引き受けなきゃ、何のために里親登録したんだ!」と奮い立ちました。
実際に受け入れてみて、いかがでしたか?

つや子さん:本当に楽しかったです。よく笑う子で、いつも機嫌がよくて。自分の子どもたちより育てやすかったです(笑)。何より無邪気な姿を見るだけで幸せな気持ちになりますよね。
俊明さん:5年経つ今でも、親子で遊びにきてくれるんです。お子さんだけ預かったこともありました。孫ができたような感じです。

つや子さん:子育てを経験したあと、だいぶ年月も経ちましたし(里子受け入れ時で二人の実子とも40代)、気持ちには余裕がありましたね。泣いてもイライラしないとか。
先ほど、児童相談所のお話が出ましたが、行政も含めて周囲の協力体制はいかがでしたか?

俊明さん:施設の里親支援専門相談員の方が何度もわが家を訪問してくれるので、気軽に相談できました。生後2ヶ月ということもあって保健師さんも来てくれましたし、心配は少なかったですね。あとは、ベテランの里親からもアドバイスをもらったりしました。

つや子さん:そろそろ自分のお家に戻るというタイミングで、お母さんが会いにきたんですけど、大泣きしてしまって。どうしたらいいのかと困って里親会のLINEグループに相談したんです。そうしたら、「実親と里親が仲良くしているのを見れば、お子さんも安心するよ」というアドバイスをもらって。実際にやってみたら子どもも落ち着きました。やっぱり経験があると違いますよね。
横の繋がりもあるんですね。
俊明さん:はい。そのLINEグループには近隣市町村の里親25人ほどが入っています。里親会では、里子と一緒に参加できるレクリエーションなども行っていて、気軽に交流できます。そうした催しやコミュニティへの参加は自由ですので、マイペースで活動できます。
実親のもとへ帰すときは寂しくなったりしましたか?
つや子さん:最初から2〜3ヶ月という打診でしたし、帰るのが前提ですので、そこまでは。どちらかというとお母さんに懐いてくれるように気を遣いましたね。何度か親のもとへ行って、わが家でどんな生活をしていたかをお伝えしたりしました。
やっていてよかったと思うのはどんなときですか?

俊明さん:一人目の里子は未だに会いたがってくれていて、お母さんからも「呼んでくれたらうれしい」と言ってもらっています。二人目の里子も原付免許取得のための勉強を見てもらいに来たり、親が進路の相談に来てくれたりと、親子ともに付き合いが続いています。そうやって頼ってもらえるのはやっぱりうれしいですね。
里親になることをためらっている人がいたら、何と言葉をかけますか?

俊明さん:大変だというイメージを持っている人は多いと思いますが、期間が短い養育里親はそんなに重く考えなくても大丈夫です。児童相談所は、体力や住環境といった条件や相性なども考慮したうえで打診してきてくれます。
つや子さん:自分の子育てと同じで、案ずるより産むがやすしですね。委託を受けるタイミングでも養育中でも、相談できる人はたくさんいますので、受け入れる前の色んな心配は取り越し苦労だったことを伝えたいです。

養育⾥親として⼦どもを養育する家庭のインタビュー動画。
⾥親になったきっかけや⾥⼦との暮らし等を紹介しています。
(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
TEL.026-235-7099
当サイトでは、サイトの利用状況を把握するためにGoogle Analyticsを利用しています。
Google AnalyticsはCookieを使用して利用者の情報を収集しますが、個人を特定する情報は取得していません。
Google Analyticsの利用規約・プライバシーポリシーについてはGoogle Analyticsのホームページでご確認ください。
なお、Google Analyticsのサービス利用による損害については、長野県は責任を負わないものとします。